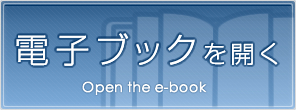Dental Products News220 page 17/28
このページは Dental Products News220 の電子ブックに掲載されている17ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「電子ブックを開く」をクリックすると今すぐ対象ページへ移動します。
概要:
Dental Products News220
2.「M T Aフィラペックス」を硬化させるにはフィラペックスのペーストとキャタリストを練和しただけでは、先に述べたように硬化したようにみえても実際は硬化していない。先のMTAアンジェラスのときに述べたようにMTAの硬化は水和反応であり、水をいかにコントロールできるかで、硬化物の性状が大きく左右される。M T Aフィラペックスはベースとキャタリストの製品構成で、特別に水分の補給についての記載はない。しかし、MTA硬化体は、混水比、練和方法、湿度に大きな影響を受ける。そこで、水分の補給をどうするか、それはどの程度か、また硬化をどのように判断するかについて、MTAフィラペックスの硬化を確かめる実験を試みた。すなわち硬化させるための要件を策定するため、根管充填材の規格としてISOでも行われる色素浸透性試験を行った。試料は、内径4mm、厚さ1mmのビニールチューブを1 5mmの長さとしたものに、M T Aフィラペックスをベース(b)とキャタリスト(c)をスパチュラで30秒間練和してチューブに填入して作製した。これをメチルバイオレッド0.25g/100mL水溶液に浸漬し、色素浸透の状況を検討した(図3)。なお、今回の色素浸透性の判定は1週間後に試料の中央部を切断してその断面で判断した。その実験結果については図4に一括して示した。コントロールは、b+c練和後室温で放置、2週間後チューブから取り出して、37℃の色素液に浸漬し、1週間後取り出した。その結果、試料の中心部まで色素が浸透し、硬化を認めることはできなかった。このことから、単にベースとキャタリストを30秒間練和し、硬化時間とされる120分待ったとしても、「硬化体」といえるものではないことが明らかとなった。このため、MTAフィラペックスを硬化させるための様々な条件を設定した。まず、A群として、ベースとキャタリストの練和時に探針の先に数滴ほどの精製水を加えて同様に2週間室温に置いたのちに、色素液に浸漬した。しかしこれもまた、硬化を呈してはいたが、極めて脆く、色素の浸透もコントロールほどではないが中心にまでみられた。そこでB群は、b+c+精製水で練和し120分後室温で水中浸漬を2日間行った後に、37℃色素液に浸漬した。その結果は、コントロールやA群とは異なり、「硬化」こそしているが脆く、硬化不十分と判定した。ここまでで解ったことは、M T Aフィラペックスを単にベースとキャタリストを30秒間練和しただけでは、硬化しないこと。そこに水を加えることによって硬化はするが、脆いものであった。さらに、水和反応を進めるため室温で水中浸漬をしても、硬化はまだ不完全であった。MTAは工業用セメントの原料であることからも、さらにMTAフィラペックスを「硬化体」としていくための、水以外の硬化因子を探ることにした。また、臨床応用を想定し図4色素浸透性試験結果ControlA群B群C群D群E群3 7℃のメチルバイオレッド0.25g/100mL水溶液に1週間浸漬し、色素浸透後の状態。付加1練和時少量の精製水を追加条件2練和後120分室温に置く32日間水中浸漬2週間室温放置2週間室温放置室温37℃37℃37℃試料の取り出し無し結果硬化しない不十分な硬化体不十分な硬化体不十分な硬化体十分な硬化体十分な硬化体Dental Products News 220 15