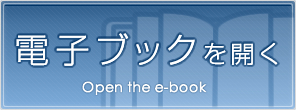Dental Products News215 page 20/28
このページは Dental Products News215 の電子ブックに掲載されている20ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「電子ブックを開く」をクリックすると今すぐ対象ページへ移動します。
概要:
Dental Products News215
日本における感染根管治療後の再根管治療率は約50%といわれており、多くの先生の実感として抜髄根管よりも「再治療」の多さを挙げるだろう。私はこれまで処置歯にできた根尖病変について「側枝やMB2の存在」「洗浄不足」「ガッタパーチャの充填不足」等、根管治療が要因であることを疑わなかった。しかしH.A.RAY.M.TROPEらが1995年に発表した論文を目の当たりにして驚愕した。なんと、再根管治療の確率は、確実な根管治療よりも確実な支台築造の方が低いというのだ。つまりコロナルリーケージのリスクをいかに減らすことが成功の鍵であると。この研究結果から再度、支台築造について根本的に考えてみた。私たちが学んできた当時の学校教育では、ポストの長さは根管の1/2を目安とすることとされてきた。しかし、予知性という観点でみてみると、長いメタルポストコアの結果として歯根破折やパーフォレーション、また前歯の再根管治療ケースのコア除去などシビアな問題を経験されている先生も多いことと思う。果たして、ポスト形成はそれほど長さが必要なのだろうか?側枝は、根尖付近に多いことは間違いないが、根管中間部で11%、根管上部でも15%ほど存在することがわかった。1mmのフェルールにおいて、ポスト長を2、5、8mmのメタルポスト、ファイバーポストそれぞれにおいて荷重試験を行ったところ、有意差は認められなかった。すなわちポストの長さは要らないということである。1本の歯にこだわるー改めて支台築造について考えようー北原 信也 TEAM東京 ノブレストラティブデンタルオフィス/東京都中央区開業支台築造の重要性を改めて知るポストの長さを再考するメタルポスト+メタルコアファイバーポスト+レジンコア荷重方向2mm 5mm 8mm 2mm 5mm 8mm8mm2mm6mm1,000(N)500図1 図21995年当時はメタルコア、リン酸亜鉛セメントでの合着であったと考えれるが、それでも根管治療の予後を左右するのは根管治療の成功よりも確実な支台築造の方が高いとは驚きである。つまりコロナルリーケージによる感染根管発症率は私たちが考えている以上に高いと言える。根管治療GoodGoodPoorPoorグループ1234支台築造GoodPoorGoodPoor成功率(%)91.4%44.1%67.6%18.1%ドイツDMG社 支台築造材料 ルクサコア Zーデュアルの活用参考文献:2)大祢 貴俊. ファイバーポスト併用レジン支台築造のポスト長に関する研究.補綴誌 2006 ; 50(2):180-190.微小漏洩長いポストだから強度があるわけではない図4フェルールとは支台歯形成限界(フィニッシュライン)から歯冠側の残存歯質量のこと。フェルールの基準は/高さ・最低1.5~2mm/形体・垂直的に平行が望ましい。※ 確保が難しい場合はエキストルージョンかクラウンレングスニングを行う。図3フェルールがない場合咬合圧によりかかる力は下方かつ開く力が生じる。いわば楔状の筒に楔を打ち込むようなものである。フェルールの存在は上からの力に対する抵抗形態となる。図5a:残存歯質は高さ1mm程度、特に歯質が薄くなり幅がない。十分なフェルールが確保されているとは言いがたい。b:フェルールが十分確保されている。a b歯質が薄くなる破折モーメントがかかる10years success rete出典:Periapical status of endodontically treaed teeth in relationto tha technical quality of the root filling and tha coronal restoration: HARAY ,M TROPE : lnt Endod j 1995(コロナルリーケージ)a:b: